特定技能受け入れの流れに関して詳しく解説
こちらのページでは特定技能を受け入れるにあたり、どのような流れで準備をするべきかを解説させていただきます。
まずは、そもそもの条件を満たしているか?を簡単にチェックします。
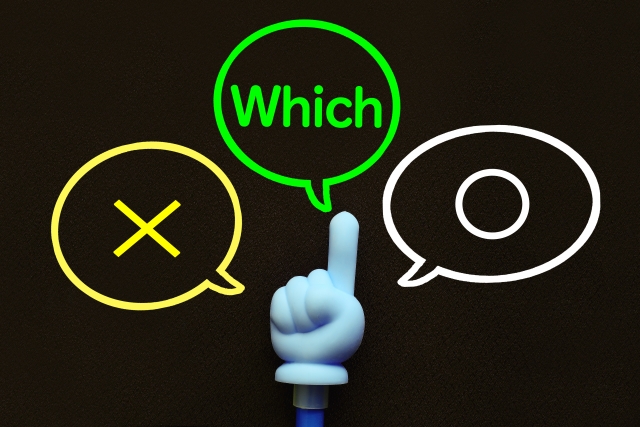
過去に入管法・労基法・労働関係法令の違反がない
特定技能を受け入れる際にまず会社の法令違反がないかのチェックをします。
基準もどんどん厳しくなっているので、例えば過去に非自発的離職者(会社都合で辞めさせられた従業員)がいた場合、特定技能の受け入れが制限されたりします。
過去に外国人雇用や労務管理で重大な法令違反をしていないことが求められます。
社会保険に適切に加入している
法律で加入義務がある社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)に、会社も外国人本人も正しく加入している必要があります。
特定技能受け入れのための申請をするときに社会保険関係の書類は提出します。
適正な賃金(同等業務の日本人と同等以上)を支払える
同一労働同一賃金が原則なので特定技能者だからとか外国人だからという理由で給料を日本人以下にすることは許されていません。
もちろん就業する地域の最低賃金や産業別の最低賃金以下に給料を設定することはできません。
とはいえ、特定技能外国人は住居など生活面でサポートされたりもするので、厳密には日本人以上の給料じゃないといけないわけではありません。
例えば職場に日本人従業員が一人しかいなく、その日本人の方は10年以上の経験で資格をたくさん保持している場合などはその方の水準まで給料をあげられないので、最低賃金やハローワークなどの求人広告の給料水準と比較されたりします。
生活サポート(義務的支援)が実施できる、または登録支援機関に委託する
特定技能外国人の生活・職場定着をサポートするため、法律で定められた10項目の支援を実施する義務があります。
こちらに関しては、登録支援機関は実際どんなことをしているのか?支援の10項目を詳しく解説のページをご覧ください。
※多くの企業はここで 登録支援機関に相談 → 委託 する流れになります。
次からは実際に受け入れが決定してからの流れになります。
(特定技能受け入れが初めての企業)協議会加入の準備

特定技能受け入れが初めての企業様に関しましては、業種によりますが企業様が協議会に加入することが求められます。例えば建設業のJACや工業製品製造業JAIMなど申請から認証まで2~3か月かかると想定すると、協議会加入は採用面接の前、もしくは同時並行で進めておいたほうが良いと思われます。協議会とは、特定技能者を受け入れるにあたり、会社が所属しないといけない業界別で必須の組織になります。最終的に特定技能の申請を入管に提出するときに協議会認証の写しが必要になります。
海外から呼び寄せ or 日本国内から転職

企業様の求める外国人材を登録支援機関にご相談いただきます。
そこで
①海外から人材を呼び寄せるパターン
②日本国内から人材を呼び寄せるパターン
のどちらかにまずは分かれます。
一般的には②国内から転職したほうが採用が早いですし、渡航費を考えたら少し採用費用は安くはなります。
ただ、国内人材ですと募集してすぐに人材が集まるとは限りません。そこはやはり住居が都会であったり、給料がすごく高ければ良いのですが、なかなかそういうわけにはいかないと思いますので、現実的には②で待ちつつ、①で安定的に海外から呼び寄せるパターンが多いかと思われます。
人材の選定・マッチング

会社の雇用条件などを提示して国内外に募集をかけ面接をします。候補者が集まったら登録支援機関は外国人材候補者の身辺チェックをします。具体的には、特定技能への在留資格申請の要件は満たしているか?資格試験合格証などの証明書はあるか?過去にトラブルを起こしていないか?(国内人材なら)きちんと税金を納めているか?などです。そこがクリアになっていれば面接に進みます。
面接は対面が望ましいですが、オンライン面接が一般的になりつつあります。
雇用契約・入管申請準備

晴れて採用が決まったら雇用契約を交わし、入管申請の準備をします。
申請人の必要な書類と受け入れ企業の必要な書類を集めて、既定の書式などで記入し最終的には100ページ以上の書類を入管に提出しますが、もちろんこれは登録支援機関がお手伝いさせていただきます。特に初回は受け入れ企業様に記入していただきたい書類や取得していただきたい書類は(納税関係や保険関係の書類など)たくさんありますが、こちらは経験豊富な登録支援機関の指示に従ってご取得していただければ問題ないと思います。
就業開始

入管から在留資格認定証明書(海外招聘の場合)や在留資格変更(国内人材の場合)の許可がおりたら就業を開始することができます。
そこで義務的支援が必要になります。
詳しくは登録支援機関は実際どんなことをしているのか?詳しく解説のページをご覧ください。
登録支援機関にご相談いただくことがスタートとするなら、スタートから大体3~6か月ほどで就業開始になるケースが一般的です。
.png)
